こんにちは。熊本県熊本市にある関歯科医院です。
最近では、小さなうちから歯列矯正を検討するご家庭も増えており、歯並びの重要性への関心が高まっています。子どもの歯並びが悪いまま放置すると、見た目だけではなく、噛み合わせや発音、さらには将来の全身の健康にも影響を与えることがあります。
しかし、子どもの成長過程における歯並びの変化は個人差が大きく、いつから気にするべきか、どの状態が問題なのかといった判断が難しいのも事実です。
この記事では、子どもの歯並びが悪くなる原因やそのままにしておくリスク、改善の必要性、そして予防方法まで幅広く解説します。お子さまの歯と健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
子どもの歯並びが悪いとどんなリスクがある?

歯並びは見た目だけの問題と考えられやすいですが、実際には健康や生活の質にも大きな影響を及ぼします。特に子どもの場合、成長期における悪い歯並びは、さまざまな面で将来的な問題の種となる可能性があります。
ここでは、歯並びが悪いことで起こり得る、具体的なリスクについて解説します。
虫歯や歯周病のリスクが高まる
歯並びが悪いと歯と歯のすき間や重なりが多くなり、歯磨きがしにくくなります。その結果、磨き残しが増え、プラークや食べかすが溜まりやすくなります。これが虫歯や歯周病を引き起こす原因になります。
特に、乳歯や生えたばかりの永久歯は虫歯になりやすいため、注意が必要です。
発音や言葉の発達に影響を与える
歯並びや噛み合わせの乱れは、発音にも影響を及ぼすことがあります。特に、サ行やタ行の発音には前歯の位置や形が影響することが多いです。
歯並びの悪さが原因で言葉が不明瞭になったり、舌足らずな話し方になったりすることもあります。
顎の成長や顔立ちに影響する
歯並びは顎の骨の発育にも関係しています。噛み合わせが正しくない状態が続くと、上下の顎のバランスが崩れ、顔の非対称や顎関節の問題を引き起こすことがあります。コンプレックスにつながる可能性もあり、精神的な影響も考慮する必要があります。
学習に支障をきたす可能性がある
歯並びが悪くて正しく噛めないと、食事に時間がかかったり噛む回数が減ったりします。食べ物をよく噛むことは脳の活性化や集中力の維持と関係があり、咀嚼が不十分だと学習に支障をきたす可能性があります。
また、噛み合わせの偏りは姿勢の歪みとも関連しており、全身のバランスにも影響を与えかねません。
子どもの歯並びが悪くなる原因

子どもの歯並びが悪くなる原因は一つではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることが多いです。ここでは、子どもの歯並びに影響を与える主な原因について詳しく見ていきましょう。
遺伝的な要因
歯並びの基本となる顎の大きさや形、骨格のバランスなどは遺伝の影響を強く受けます。両親のどちらか、あるいは両方が歯並びに問題を抱えていた場合、お子さまにも同じような傾向が見られることが多いです。
特に、顎が小さいと歯が並ぶスペースが足りず、歯並びが乱れやすくなります。
虫歯などによる乳歯の早期喪失
乳歯は永久歯が生える位置をガイドする大切な役割を持っています。そのため、乳歯が虫歯などで早く抜けたり、抜歯せざるを得ないほど悪化したりした場合、永久歯が正しい位置に生えてこられなくなり、歯並びが乱れる原因になります。
指しゃぶりや舌の癖
指しゃぶりや舌を前に突き出す癖、口を開けたままにする癖(口呼吸)なども、歯並びに悪影響を与える習慣です。これらの癖が長期間続くと、前歯が前方に押し出されたり、上下の歯が噛み合わなくなったりすることがあります。習慣に気づいたら早めに対処することが重要です。
食生活の乱れや咀嚼不足
現代の柔らかい食事や食習慣も、子どもの歯並びに影響を与えています。噛む回数が少ないと顎の発達が不十分になり、歯が生えるスペースが確保できずに歯並びが悪くなることがあります。
硬い食材を取り入れる、よく噛んで食べるといった食習慣の見直しが、歯並び悪化の予防につながります。
口呼吸や鼻づまりの影響
慢性的な鼻づまりやアレルギー性鼻炎などによって口呼吸が常態化していると、舌の位置が下がり、上顎の成長が妨げられます。これにより歯列が狭くなり、歯が重なりやすくなります。耳鼻科での治療や口呼吸の改善トレーニングが必要になる場合もあります。
治したほうがよい子どもの歯並び

すべての歯並びが治療の対象になるわけではありませんが、将来の健康や生活に悪影響を及ぼす可能性がある場合は治療が推奨されます。見た目だけではなく、噛みにくさや発音のしにくさなどの機能的な問題を伴う場合は特に注意が必要です。
ここでは、早めに矯正治療などの対応を検討したほうがよい歯並びについて解説します。
出っ歯(上顎前突)
前歯が大きく前に突き出している状態を出っ歯と呼びます。出っ歯の場合、転倒時に前歯を折るリスクが高くなったり、唇が閉じにくくなることで口呼吸につながったりする可能性があります。発音や食事にも影響するため、改善が望ましいケースといえます。
受け口(下顎前突)
下の前歯が上の前歯より前に出ている受け口は、放置すると咀嚼機能や発音に影響を及ぼすだけではなく、下顎が過度に成長して顔の輪郭が変わることもあります。幼少期からの対応で改善が可能な場合もあるため、早期に相談することが大切です。
開咬
奥歯で噛んでも前歯が上下で開いたままの状態を開咬(かいこう)といいます。指しゃぶりや舌の癖、口呼吸などが原因で起こることが多く、発音や咀嚼への影響が大きいのが特徴です。
食べ物を前歯で噛み切れない、発音が不明瞭になるといった問題がある場合は、治療が必要とされます。
乱ぐい歯・叢生
歯が重なり合ってガタガタに並んでいる状態を乱ぐい歯、または叢生(そうせい)と呼びます。この状態は第一印象にも影響しますが、それ以上に歯磨きがしにくくなるため、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。
歯列矯正によって清掃性を改善し、将来的なトラブルを防ぐことが重要です。
交叉咬合
上下の歯が横方向にずれて噛み合わない状態を交叉咬合(こうさこうごう)といいます。片側ばかりで噛む癖がつきやすく、顎の骨の成長バランスに影響を与える恐れがあります。顔の左右差や顎関節の問題にもつながるため、専門的な治療が必要になります。
子どもの歯並びが悪くなるのを防ぐ方法

子どもの歯並びは、遺伝的な要素だけではなく、生活習慣や環境によっても大きく左右されます。歯並びが悪くなる前に日常生活の中でできる予防策を取り入れることで、将来的な矯正治療の必要性を減らせます。
ここでは、子どもの歯並びが悪くなるのを防ぐために家庭でできる対策を紹介します。
正しい姿勢と噛み方を意識する
子どもの歯並びには、姿勢や噛み方も大きく関わっています。足が地面につかない状態や前かがみの姿勢は、顎の正しい発達を妨げます。また、片側だけで噛む癖がついていると、顎が偏って成長することもあります。
イスやテーブルの高さを調整し、両側の歯でしっかり噛む習慣を身につけましょう。
指しゃぶりや舌癖を改善する
3歳を過ぎても指しゃぶりが続いている場合は、歯並びや顎の発達に影響を与える可能性があるため注意が必要です。また、舌で前歯を押す癖や、舌を出す癖も歯並びを乱す原因となります。
子どもに負担をかけず、遊び感覚で癖を改善する方法を取り入れると良いでしょう。
鼻づまりや口呼吸を改善する
鼻炎やアレルギーによって慢性的に口呼吸になっていると舌の位置が下がり、上顎の成長に影響が出て歯列が狭くなる原因になります。口呼吸は虫歯や風邪のリスクも高めるため、耳鼻科での治療や口を閉じるトレーニングなどで早めの対処を行いましょう。
よく噛む食習慣を育てる
現代の食事は柔らかいものが多く、噛む回数が少なくなりやすいです。顎の骨を育てるには、しっかり噛むことが大切です。食材の硬さや大きさを工夫して、自然と噛む回数が増えるようにすると良いでしょう。
例えば、にんじんスティックや干し芋などをおやつにするのも一つの方法です。
定期的に歯科健診を受ける
子どもの歯並びの問題は成長過程の中で徐々に現れることが多く、家庭では見落されやすいです。小児歯科での定期的なチェックを受けることで、早期発見・早期対応が可能になります。歯科医師に相談することで、必要に応じて適切なアドバイスをもらえます。
まとめ

子どもの歯並びが悪い状態を放置することは、虫歯や歯周病のリスク、発音や咀嚼の問題、顎の発達や姿勢への影響など、さまざまなリスクを伴います。歯並びの乱れには遺伝的な要素だけでなく、指しゃぶりや口呼吸、咀嚼不足といった生活習慣も深く関わっています。
子どもの将来の健康と自信のある笑顔のために、歯並びの状態を日ごろから意識し、必要な対応を取ることが大切です。また、気になることがある場合は、早めに歯科医師に相談しましょう。
子どもの矯正治療を検討されている方は、熊本県熊本市にある関歯科医院にお気軽にご相談ください。
当院では、インプラント治療を中心に虫歯・歯周病治療、矯正治療など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、WEB予約もお受けしております。

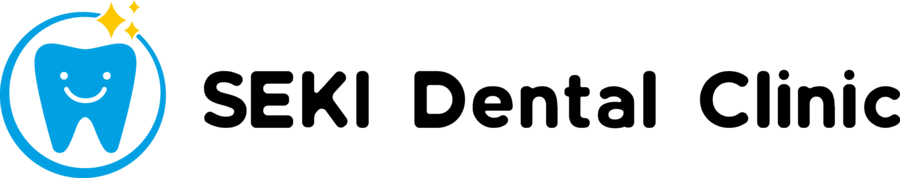





 お電話
お電話